オノマトペでフランスを斬る 日仏オノマトペ研究より: 真泉 薫
絵:ダヴィッド・ケン
blabla!(7)
息子の誕生日、ギターとセーターと決めてお店に一直進!ギターは息子と決めることにして、セーターは親の好みだからね。 たまにはクラシックに決めてもらおう。
クリスマスの後だから、いいものはあんまり残ってはいない。それでも、これにしようとすいたお店の会計の前に行くと 回りは誰もいない。早く帰ってケーキが作れると、喜んだもつかの間、男の店員と女の店員はお店のど真ん中で Bla Bla(ぶらぶら=ベラベラ)お話なさって、一向にこっちに関心を寄せない。Bla Blaお話しながら客がひっくり返した セーターをたたんでいる。こっちに買う客がいるんですよと咳き込んでみた。 やっと、こっちに気づいたのはいいのだけどまるでゾウさんのように歩いてくるではないか。ちょっといい加減にして!
こっちの店員は皆さんもお気づきでしょうが、こっちからこんにちはと挨拶しないと機嫌が非常に悪い、 時には人に話しかけるときはこんにちはと言ってからよと。御注意をくださる店員もいる。私はそんなとき、 さようならと帰ることにしている。 でも、今日は帰れないの。これを買うまでは。ゆっくりレジをなさって、はいと放り投げるようにくれるではないか。 あのうプレゼント用なんですけど、、、女の店員曰く、クリスマス後なので箱がない。そんな今日必要なんだから、 なんか方法があるでしょう。ないものはないと切り出した。ふと、ウインドウに目をやるとクリスマス商戦用に飾り のカラのプレゼント箱がつるしてあるではないか。これだと思ってそれに入れてくれとお願いすると、今度はこれは 使えないときやがる、ううっ、おまけにこれを使うと店長に明日叱られるとか、こっちも負けずにじゃあ明日叱られたら、 私に電話してと、無理やり電話番号を残す。やっと勘弁したのか、箱に入れてくれたが、埃の着いたまま,拭きもしない。
まあここまで望むのは無理か。 家で拭けばいいか。店員はまたもとの位置に戻り、さっきの男の店員とBlaBla、いいなあ、ここはフランスなんだ。 誰も焦りはしない。臨機応変にしやしない。 こっちもぶらぶら帰ってゆっくりケーキを焼くことにするか。
*ぶらぶら(雄弁という意味)のように同じ言葉を繰り返すフランス語はオノマトペの中でも幼児語として取り扱われる。
BEURK!(6)

ある日、街の歩道を歩いていたら、運悪く犬の糞を踏んでしまった。
隣にいた息子がすかさず “BEURK ! ” うえっ。 もうまったく、これだから土足で入るフランスの家はいやなんだ。きれい好きを自称している国で何故こうも犬の糞が あちらこちらなんだろう。市は糞片付けに毎年相当の額の予算を使っているらしい。しかし一向に減らないという。
私だったらまず小学校にお掃除おばさんを雇うよりフランス人の秩序教育にお金を掛けるけど、なんていいたくなる。 よく日本人の台所を見て“なんて汚いの”なんて口にされる方々、しかし、台所は私有地の範囲、公共の地を汚しておいて、 人におせっかいできるのだからフランス人の意識はどこかへん?
カフェなんかで平気でコーヒーについてくるチョコの包み紙を破っては足元に捨てているパリジェンヌさん。
これっていくら 最後には床を掃除する人がいるからって、次にその場に来るお客を無視しすぎていません。せめて灰皿に入れていただきたい。 見ているこちらが捨てに行きたくなる。決まってフランス人の言い訳は掃除をする職業の人の仕事を残してやっているのさと。
“BEURK ”は“BERK ”とも発音される間投詞、感嘆のオノマトペ。うえっ、おえっと同様に何か汚いものをあらわすときに使用される。
しいて言えば“B ”と“R”がひとつの言葉として使われるとき、その意味は汚いものが多い。 これと同意的に使われるのが“MERDE”くそっ、(糞)でもこの言葉は日仏共通していると思われる。しかしフランス語のそれはまず 音から始まり−言葉ができ−動詞になり−助動詞になるという風に変化してきた。それに比べ日本語のオノマトペはまず、 音あるいは感覚により−言葉ができ−言葉から動詞、形容詞、助動詞などが生まれたと思われる。
動詞や形容詞が同じ言葉で 共通してるとは限らない。フランス語は残った音をそのまま間投詞とした事実がある。 MERDEは糞 またはMERDOUILLE 窮地−動詞はMERDER しくじる またはMERDOUILLER まごつく−助動詞はMERDEUSEMENT 情けなくも−形容詞はMERDIQUEひどい、つまらない MERDEUX くだらない、けがらわしい またはMERDOIE 黄緑色の などなど 糞の言葉からよくこれほどの言葉を生み出したものだ。
ティッシュを出して丁寧に拭けたと気持ちを改めていたら、今度は学校の前でまた糞を踏んでしまった。息子は即座に “DE LA CHANCE ”(今日はチャンスがあるね)と変な慰めをしてくれた。犬を連れたお母さんの手元にビニール袋がないのを確認して、 その側で“MERDE”と大きな声をあげていた。
CLAC(5)
 ある晴れた夏の日なのに街はなんとなくにぎやかさを失っていた。
そうかみんな海や山へヴァケーションに行っているんだ。サマーバーゲンも一段落し、
やっぱり今年も買わなくていいものまで買ってしまった失敗組みは街に残り長い夏休みを
映画やレストラン等で気を紛らわせている。
ある晴れた夏の日なのに街はなんとなくにぎやかさを失っていた。
そうかみんな海や山へヴァケーションに行っているんだ。サマーバーゲンも一段落し、
やっぱり今年も買わなくていいものまで買ってしまった失敗組みは街に残り長い夏休みを
映画やレストラン等で気を紛らわせている。友達と久しぶりに逢ってレストラン選び、 歩道にまでテーブルや椅子を並べているわりに
店内には客はまばら。 よしここなら自由に席が選べると静かなそれでいて歩道を通る人を見渡せ明るいその場所に 丸テーブルが置かれている。軽くその場所に案内してくれるように申しでて席を取ろうとしたとき、 何人かと聞かれ4人と答えるとここは5人席だから他の
テーブルにという。 ここが気に入ったからと言ってもだめ、ついには給仕などがひっきりなしに通る席に案内され、 おまけの言葉まで頂いた。食器をガチャガチャならしながら、ここが気に入らなければ 他にレストランはあるとまで言われたのだ。それなら他に行くと立ち上がると給仕は食器をかたずけ、 厨房に入りドアをバタン!耳が破れそうになった。
これってフランス語ならClicだろうか、 Clacだろうかと考えたとき、どちらにしても迫力がかけている事に気づいた。 フランス語のオノマトペはJean−Pierre GIRAUDが著書“オノマトペの構造”の中で書いているが、 たたく音から出来た語は母音のIと子音のKの音、母音のAと子音のKの音が多いそうだ。 時計のチックタックなどもその一例だろう。
Claquementクラックマンとはタップダンスのそれ、 でも今の心境はこんなやさしいものではない。
結局、すぐ近くに同じようなレストランを見つけ、 満足がいった。そこを出て例のレストランの前を通るとやっぱりあの丸テーブルの席は空いている 。私たちをあんな形で追いやった人の前に行ってこっちも戸をバタンと閉めてやりたかったが、 時には優雅さを見せるのも悪くない。彼がこっちに気づいたときしっかり聞こえるような声で “Tete a claques(嫌な面)”とわざと言ってその前を過ぎた。
BOBO(4)
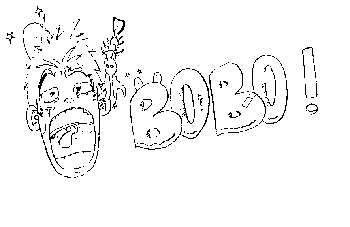
公園のベンチに座っていると、どこからとなく幼い子供が駆け寄ってきて
“MAMAN BOBO”(ママン、痛いよ)と転んだときの傷を突き出しなががら甘えている。
ママンはすぐさまおしゃべりをやめて、手についている土をはらいながら “何でもない、何でもない”と少し勇気づけるとなんとなく納得した幼児はまた走って 他の子どもたちに交じって行った。
日本なら“痛いの痛いの飛んでいけ”だろうかなんて 考えながらほほえましげな光景を見ていた。
この“BOBO”(ボボ)はまさしく“MAMAN”、 “PAPA”に筆頭する幼児語のオノマトペなのだ。では言葉に起源があるならこれはいったい何なのだろう。 辞書にはただ幼児語と記しているにすぎないが、実によく大人の社会で耳にする立派な言葉になっている。 痛いとなれば、“Aie”が使われるが“BOBO”は小さな傷、ちいさな痛み、小さな過ちなど広い意味で使われている。
最近では、“BOBO”のBOの最初の字だけをもじって“BOURGEOIS BOHEME”と使われることがたびたびある。 つまり、ちょっと生意気なブルジョア階級の若者がボヘミアの自由奔放な精神を持ちたいという表れなそうだ。 最近のフランス映画“TANGUY”を見た人はおわかりになると思うが、 30歳を過ぎても親元を離れないリッチな息子の追い出し作戦を展開する両親の苦労を滑稽に描いた物語なのだが、 笑ってしまうだけではいられないそんな危ない世相になってきているのも事実だ。 日本でもフリーターという職業を抱えた大きな子供が問題になってきている。 ここ、大人の世界だったフランスも子供を追い出せない、叱れない親は確実に増えてきているのが現実だ。
ある日、大人の顔をした、頭の中身が幼児のそれと変わらない人間がママン、ボボと言ってくる その恐怖を感じざるを得ない。
EH!(3)
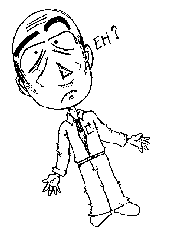
クリスマスは家族と、大晦日は友達と過ごすのがフランスでは当たり前のようになってきている。
うちもそれに倣って毎年長男の嫁としては義母をラ・ボールの町から呼ぶことになるのです。 3日はあっという間に孫の話しや義姉の話しなどで過ぎるのでどうにかなるのだけれど 徐々に何を話して良いか。そうすると出てくるゲームが スクラブル。つまりアルファベットの文字をつなぐ言葉遊び。 格子盤にはすでに何箇所かに2倍、3倍になるようにセットされそれぞれの文字に さまざまな点数が付いていて点数の多い言葉を作ると勝ちになる。
向こうは生まれてから孫が出来るまで立派なフランス人こっちは 20代の後半からフランス語をやり始めた未熟者。でもそれはそれエイッと「ZEN」なんて言葉を 2倍のところに乗せ一度に24点を稼ぐ、それしか手がない。 あちらもけっして長い形容詞や複数形など使わず「EH」を3倍のところに並べ喜んでいる。
あれっこれってオノマトペではありませんか。しかも間投詞のそれなのです。 彼女は辞書にあるからと平気。もうこうなると言葉がいきずまり 大変なので何とか長い言葉を作るのに時間がかかると「3分ぐらいが規則よ」 ときっちり攻撃がかかる。そうおっしゃれても先ほどは夕食の準備をしながら 15分も待ったのはこっちなんですけど。なんて言い返したくなる。
それをぐっと抑えて最後にのこった「E」を「H」の右横に置こうとしたら「EH 」はあるけど「HE 」 とはいわないのよ」 今度スクラブルの辞書を買ってからにしましょうと、しかも 「あなたとやるとごまかされてばかり」とおまけの言葉がついて逃げられてしまった。
「ええっ」そんな馬鹿な。合計ではこっちが勝つのにゲームを放棄。 フランス人の性格にはおっと義母の性格には本当に唖然。
地球の裏側から来た日本人に負けても恥ずかしいことでもあるまいか。 ついでに言わせていただければ「He」も立派な間投詞ですぞ。
ATCHOUM(2)

夏もそろそろ終わりフランスは急に秋に入る。 入るといってもフランスに長く暮らしている人はおわかりかもしれないが、 すぐにオーバーやコートの準備をしなければならない。 だってここは日本に比べて春も秋もきわめて短いからだ。 ハックション!どこかで大きな声がすると、 ついこれは日本人だなと想像してしまう。フランス人のそれは「ATCHOUM!(アチュウム)」 何か気が抜けると思わないか。 日ごろ大胆に振舞っているフランス人がこと自然の成り行きになると気が小さいのだから。
フランス語の先生を京都で2年間した金髪の女友達は京都の冬をこう語る。 教室でみんながいっせいに鼻をグズグズ。でも誰もかまないのよ。 どうして。かめばすっきりするだろうに、 とまるで鬼の首を取ったかのように毎回日本人の癖として話すのである。 フランスの諺で「Qui se sent morveux se mouche.」 (洟が出ているとわかったら洟をかめ)つまり、 人に注意されたら行いを正せという意味があるそうだ。 その反対が日本の諺で「鼻たれ子も次第送り」だ。 注意しなくとも次第に一人前という意味。
でも、案外個人主義のフランス人は他人に注意なんかすることはない。 どんなに郵便局などでカウンターの向こうでこっちが列を作ろうと 一向にかまわないでベチャベチャおしゃべり。 一言お客が帰ってからにしてはなんて言うのは日本人くらいのものだろう。 他人に注意しない傾向は日本社会にも出始めているようだが。 どちらにしてもフランス人のように所かまわず何度もかんだクシャクシャのハンカチーフを出して 一言の謝りもなくかむ姿を私たちは嫌うのだと思う。
ATCHOUMはオノマトペでも日本語の擬音語と同じであるから、 人間は体の仕組みが同じ上、同じように聞こえなければならない筈。「H 」の発音がされなくなったのは フランス人の言語の特徴のようだ。 理屈っぽいフランス人に「R 」の発音などで馬鹿にされるとき必ずじゃあこの発音をどうぞ 「はい」とはっきり言ってと切り出す。 ほら言えないじゃないの。誰も足なんか踏んでない。だから「aie!」 なんていうのはやめてほしい。わかったでしょ。
耳がイタイのは何度も発音を直されているこっちなんだから。
cocorico(1)
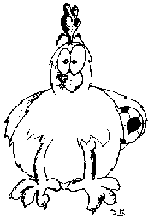 ああ、なぜ日本人とフランス人の感覚はこうも違うものかとフランス滞在
3年目ぐらいから考える人は多い筈。2年目はフランス語を習わなきゃと気合が入っているので
あまり考えないようだ。それともあなたは1年目から「もうっー」とイライラしているのでは。
ああ、なぜ日本人とフランス人の感覚はこうも違うものかとフランス滞在
3年目ぐらいから考える人は多い筈。2年目はフランス語を習わなきゃと気合が入っているので
あまり考えないようだ。それともあなたは1年目から「もうっー」とイライラしているのでは。そうですこのイライラが日本語特有の擬態語つまりオノマトペなのだ。 でも考え方によれば、いえ研究によれば、どこの国に居ようと人間なんて同じ感覚をもっているそうだ。
イライラをフランス語に訳すならS’IRRITER,S’ENERVERだろう。特に最初のイリテなんてどこか イライラに似ていないだろうか。しいて言えばイリイリかな。ヒリヒリすることをやはりIRRITERともいう。
辞書では、オノマトペはギリシャ語のオノマあるいはオノマトス(言葉)とポアエイン(創作する)から出来たそうだ。 シャール・ノディエ氏* は「フランス語オノマトペの論理辞典」で現在使われている言葉はもとはすべてオノマトペから来ている と言う説を昔に出した人だが、フランス人は残念なことにオノマトペを実際には間投詞と 幼児語としか見ていないようだ。そんな大人ぶったフランス人。でも、どこかのテレビ 放送でギニョール(人形芝居)でしか政治を批判できなくなっているのは大人としてどこか変。
オノマトペはもしかしたら地球を救う唯一つの言葉なのだと私は信じている。
ところで、スポーツ界で よく飛び出してくるのが雄鶏。フランス国の象徴といえど何かうるさい存在のような気もする。 その雄鶏の鳴き声が日本語ではコケコッコー。この泣き声を世界中で比べるとと少しずつの違いがある。 環境、生活の違いで人間は言葉の変化を少しづつ遂げてきた。音声上殆ど「O 」「I 」「U 」 の発音の多い組に分かれるのだ。ポルトガルではCOCOROCO イタリアではCHICCHIRICHI ドイツもKIKERIKI, スエーデンではKUKELIKU, ロシアもKUKARIKU。グループ分けするとフランスとポルトガルそして日本、 イタリアとドイツ、スエーデンとロシア・・・ もちろんこれは偏見であるが。もうおわかりかとおもうが文句が多いのはフランス人に限った事ではなさそう。
ちなみに朝鮮語ではKOKIO中国語はKOKOKOだそうだ。
*Charles NODIER ≪ Dictionnaire raisonne des onomatopees francaises ≫ en 1808.
ホームへ